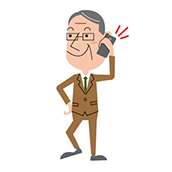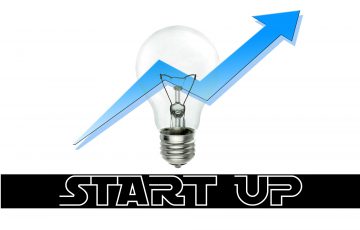社長業は孤独で、日々のストレスも一般の人とは比べものにならないほど大きい。だから社長には、その重圧に耐えられる精神力が要求され、孤独やストレスといかに向き合うか、いかに親しく付き合うかが重要なポイントとなる。たとえばストレスに苛まれる自分を俯瞰して、他人事のように観察する、苛立つ自分を別の自分が距離をおいて眺めるという方法がある。こうしてストレスの正体が分かってみると、案外それをすり抜ける道も開けてくる。
社長以外の人間にできない仕事こそ「社長の仕事」である。「方針」を立てることは優秀な部下に任せることもできるが、「責任」は社長が取るべきものであり、社長の責任逃れは決して許されない。「責任」と同様に社長にしかできない仕事が「決断」である。経営の厳しい場面では、材料が十分に揃わない時点で、一定の方向を出さざるを得ないことが多い。ここで問われるのが「決断力」である。逡巡は会社を危うくする。
さて「決断」とは、たとえ判断材料がわずかしかない場合でも「やる」か「やらないか」を決めることであり、「決定」とはもともと性質が異なる。当然迷いも多いが、それを決めるのはトップの強い意志である。ただ経営は博打ではないから、冷静に事実を見て熟慮する必要がある。正しい「決断」をするために重要なのが「衆知独裁」である。雑音を含めた多様な意見を聞き分け「些事」に惑わされることなく、そこに隠された事実を見極め、強い意思をもって「決断」する。社長の「独裁」は必要ではあるが、社長は「独断」に走ってはいけない。一人の知恵で判断し、一人で決める「独知独裁」ではなく「衆知独裁」が求められる。度が過ぎたワンマンでは、組織力を結集することは難しい。言いたい放題こそが本当の和を作るのである。社長は極力発言を抑え、幹部が自由に意見を提起できる場をつくるよう心掛けるべきである。
会社を構成する多種多様な社員を束ねる社長には、相応の器量の大きさが求められる。社員は「同じ釜の飯を食う仲間」であると同時に「生産性を上げるための機能(道具)」である。社員に「仲間」と「機能」の両面があるのだから、社長は「炎のごとき熱さ」と「氷のような冷たさ」を巧みに使い分ける二重人格者でないと務まらない。つまり「仏の顔」と「鬼の顔」を併せ持つことが、社長には求められる。
ただ人間をシビアに見ることは大切ではあるが、不信感を抱いていることが部下に伝われば、組織の求心力は失われる。またいちいち指示をしていれば、そのうち指示がないと動かなくなる。だから社長は重箱をシャモジでザックリとすくって、すくい切れないところは部下に任せる位が良い。それが人を動かすコツである。同時に社長はモノゴトの本質を見抜く目をもつことが大切である。その前提は何事も「大きく捉える」ことである。大きく捉え、打つ手は小さくても効果の高いところから行う「大局着眼、小局着手」が有効となる。
経営にとって「ヒト」は財産である。人間の潜在能力は無限であり、才能や潜在能力を引き出すことができれば、ヒトは思わぬ力を発揮する。つまりヒトは「化ける」のである。組織運営で大切なのは、いかにヒトを「化け」させるかである。その潜在能力を引き出し、本人に気付かせる手法として「異質の体験」をさせることがある。冴えない仕事ぶりの社員が、まったく異なる環境に放り込まれることで、才能を開花させることは非常に多い。
会社の組織運営で、「人事」は重要な経営案件である。人間は感情の動物だから、よく納得させることが必要である。「人事が才能をつぶす」こともあり「腫れ物に触るがごとく」が人事の要諦である。人事権は社長の最大の権力であり、人事権のもつ重みを社長は認識するべきである。自分に反対する人間など、どこかに飛ばしてしまえば良いのだから、社長は自分の好きなようにできる。人事権をもつ社長は、よほど意識して「権力の魔性」をコントロールしないと、権力者であることが自滅をもたらすことになる。人事による悪影響はすぐに蔓延し、組織の一体感が薄れることになる。だから社長には、したたかに「人を見る目」が求められる。業績だけを見て地位を与えると、社内に思わぬ動揺を与えることにもなる。「功ある者には禄を与え、能ある者には地位を与えよ」という言葉は、人材発掘・後継者育成という点で示唆的である。ただ人事は難しく、慎重に行わなければならないが、人事にベストはなく、ベターな人事を考えればよい。つまり6割程度の範囲で適任と判断したら「よし」とするのである。
ただ査定の公平さを維持するために、自信をもって判断できる健康状態を社長は維持する必要がある。特に役員人事を決めるには、一年間かけて考えるほど慎重になる必要がある。まして後継者の人選には十年かかる。まず最初の三年で候補者を絞り、次の三年で地位を引き上げていろいろな仕事をさせ、もう三年かけて社長として通用するか最後の絞り込みをする。そして最後の一年はバトンタッチを前提とした併走期間とする。きちんとした計画性と理念をもって後継者を育成しないと、十年はあっという間に過ぎ去る。人間を100%理解することは不可能ではあるが、人事ではできる限りそこに近づくための努力が求められる。
権力は十年も経てば腐敗する。権力を持つ人間に対する周囲の気遣いや思惑が、その人間をおかしくするのである。悪い報告や社長批判など上がってくることはなく、社長は裸の王様になってしまう。社長が不機嫌になるような情報は届かないことを、社長自身が自覚しているかどうかが大切である。社長の意見や提案がほぼ通ってしまうと、本人は気持ちがいいが、自分はいつも正しく、その考え方は全員に理解されていると考えるようになる。社長という地位に権力がついているだけなのに、そのことに考えが及ばなくなり、自分を見失って正しい判断ができなくなる。それが社長個人に留まらず、会社全体に及ぶことになるほどに、権力は怖い。「権腐10年」は社長業の戒めとして、心すべきことの一つである。「権腐10年」を避けるために、イエスマンのブレーンを変えたり、社長の報酬を報酬委員会で決めるなど「すべてが社長の思い通りにいくわけではない」仕組みを入れることも一案である。
社長業にリスクはつきものであるが、問題はどの程度のリスクなら背負えるかというバランスにある。経営は「何があってもいいように」コンティンジェンシー・プラン(危機管理対応計画)を持ちつつ進めるべきだ。結果として「何もなかった」にしても、そこに至るまでにどういう手が打たれたかが大切で、「何もなかった」と「何もないようにした」では雲泥の差がある。
会社の命取りになりかねない案件に、借金・投資・契約が挙げられる。しかしこうした経営を左右する重要な項目が、明確な原則がないままに流されるケースが意外と多い。これも組織運営の難しさで、社長が陥りがちな落とし穴と言える。限度主義は経営の要諦であり、「限度」を前提とした社長の考え方が重要になる。堅実に成長する会社は、経営に関わるすべての項目について、社長自らが「限度」を設定し、それを頑なに守っている。
社長の心得として、悲観的に準備し、楽観的に行動することが重要な要素となる。周到に、かつ悲観的に準備しておけば、当てが外れたとしても慌てふためくことはない。時には思い通りにいかないこともあると割り切って、その大変さを楽しみ、実行に移した後は楽観的に行動すればよい。段取りの狂いや判断に誤りがあったとしたら「スピード」と「行動力」でカバーすればよいのである。
経営は「経験科学」であり、そこには一定の原理原則があって、その積み重ねによって会社は運営される。「思わぬこと」に左右される面はあっても、それはあくまでもレアケースであり、潰れる会社は潰れるべくして潰れる。人間に「人徳」があるように会社にも「社徳」があって、経営では案外これが大切な要素になる。似たような環境にありながら、一方の会社は生き残り、一方の会社は倒産の憂き目に遭う例は珍しくない。その境目を決めるのが「社徳」であり、「社徳」が「運」や「ツキ」を呼ぶのである。ここでいう「社徳」とは、取りも直さず社長の「徳」である。会社は潰れるようになっている。それを防ぐには、社長が誠心誠意、社業に向かい、自らを磨くことが基本となる。勉強も必要だし、「決断力」を高め、「先見力」を磨き、人材育成にも力を注ぐ。財務バランスを整えるための努力も求められる。こうして「社徳」を積むことが、会社を支える一つの方法となる。公私混同で「会社は自分のもの」と考えている社長の下では、「社徳」は育まれないし、会社も存続できない。社長は常日頃から「社徳」を積み、まずは足元を固めるという心掛けが大切になる。
また会社には「社風」というものがある。「社風」とは、会社の組織力に直結する大切な会社の体質である。ところで「社風」を変えようと躍起になっても「澱」のようなものがあって、いっこうに変わらないと言う社長がいる。これは「社風を作るのは社長自身」という簡単な理屈がわかっていないのである。社長の「価値基準」や「判断基準」が「社風」となるわけで、社長のリーダーシップと熱意があれば、「社風」を変えることは難しくない。社長の言動から、会社の規範である「価値判断基準」を社員は感じ取るのである。社長があらゆる機会を通して、自らが考える「我が社の価値判断基準」を行動や言葉によって繰り返し伝えることが「社風」を作る。社長の思いの強さが、会社を伸ばすのであり、その「思い」を絶えず社内に語りかけることで、人や組織は動くのである。
行動力のある社長は「現場」に出ることを厭わない。「現場」とはお客様と接触している会社の最先端であり、そこには情報が溢れている。その「現場」に出ることで、お客様の声に近づき、社員のナマの意見を吸い上げることができる。「社長は現場に詳しくないといけない」は経営の原則である。経営は実践学であり、「現場に情報あり」は経営の鉄則で、たえず現実と向き合うことが大切である。データは経営に不可欠ではあるが、データの背後にある細かい機微がわからないと、大きな落とし穴にはまることになる。また「経営は環境適応業である」という言葉があるように、いかに世の中の変化に合わせていくかで、社長の力量も決まる。新しいことに敏感であることは、社長に必要な条件である。つまり変化を楽しみ、すべてにおいてパターン化することを排除するのである。行動パターンを崩すことによる変化に新鮮さを感じ、心躍らせ、自ら脱皮することが、社長には大切である。
経営では「利益率×回転率」が重要となる。利益率の高い商品・サービスを扱うことがポイントではあるが、高い利益率が期待できないなら、せめて回転率のいい商売をしないと経営は成り立たない。また経営を軌道に乗せるには、最低でも月次決算を行い、月次で業績をコントロールすることが大切である。固定資産を持たず、現金商売で、粗利益率も回転率も高い商品・サービスを扱い、毎月の月次決算を欠かさない、これが経営のコツである。
不景気な時代に業績を伸ばす会社は、懸命に知恵を働かせている。「目のつけどころ」が勝負の分かれ目となる。たとえば中小企業の場合、まず30%の自己資本比率を目指す必要がある。次に狙う目標は50%である。自己資本が50%あれば、借入金を当てにしないで経営ができるようになる。そして自己資本比率が70%になると、実質的に無借金経営が可能になってくる。自己資本比率を上げるには、第一に利益を出し内部留保すること。第二は配当の問題はあるが増資すること。第三の方法は、資産の中身を筋肉質にして余計なものを削ぎ落とし、企業体質をよくすることである。会社が小さいうちは配当や役員賞与をゼロにして、会社の体力をつけることが明日の成長につながる。
資金作りに妙手はなく、基本は貯金である。そこで必要なのが「天引き」の発想で、たとえば100万円の利益が上がったら、10%に相当する10万円を自動的に貯金し、事業資金に回すのは残りの90万円にする、というルールを確立する。苦しい経営の中で事業資金を削るのは厳しい。しかし事業資金からカットした分を補填するために、売掛金回収を促進したり、在庫の圧縮、経費節減などの手を打ってカネを生み出し、貯金を捻り出すのである。中途半端なまま資金不足を借金で補おうとすれば、いつまでたっても借金体質から抜け出すことはできない。デフレ経済では、借金は会社を成長させる原資ではなく、成長の足を引っ張るものである。
資金繰りが逼迫していて余裕がないとしても、やり方次第である。たとえば利益を出していない商品を切り捨て、多少なりとも利益を稼ぐ商品に会社の資源を投入する「選択と集中」によって、販路拡大・収益性アップに全力を傾けるのである。小回りのよさに特化して資源を投入することはリスクを伴うが、中小企業は少ない資源を一点に集中したほうが勝てる条件は広がってくる。こうした戦略の決定はいかに的を絞り込むかであり、迷いを断ち切ることが前提になる。ただこうした決定は、社長の強権なくしてはできない。戦略の実行は「重点的に」「集中的に」「徹底的に」行うことが大切で、これは社長でないと決められない。
著者:田辺次良氏 (出版社:ダイヤモンド社 )より